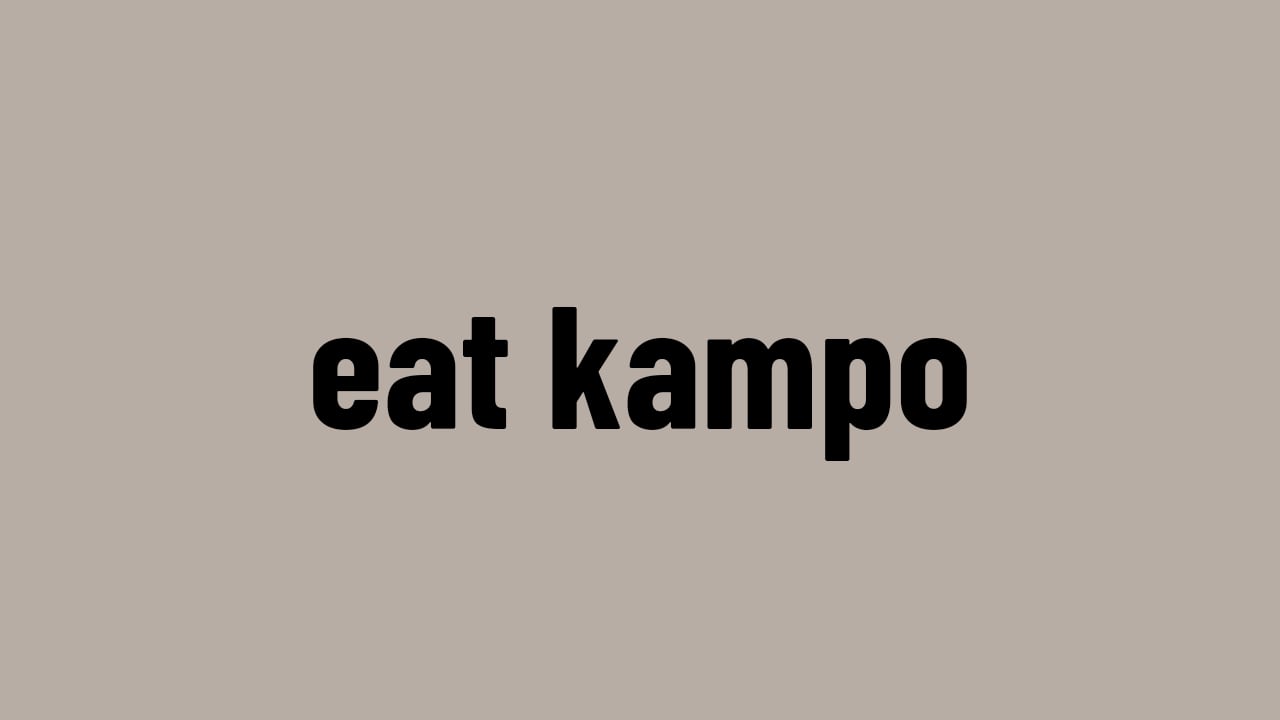2022/11/06 10:20

明日11月7日は『立冬』
冬の始まりの日です
今回は漢方でみた冬の季節や過ごし方についてお話していきます
〇漢方でみる冬と『腎』
漢方では冬は五臓の『腎』と関係する季節。
『腎』は腎臓としての水分代謝を担うだけではなく
生命力の源である《精気》というエネルギーを蓄え
成長・発育・生殖というヒトが生きるための大切な役割を担っています。
腎に蓄えられた精気は年齢とともに減っていき
これが完全に無くなることが死に至るとされています。
また、加齢に伴って現れやすくなる
関節や骨が弱くなる、耳が遠くなる、白髪、頻尿、
こんな現象も腎が弱くなり蓄えられる精気が減ることが原因と考えます。
裏を返せば
いつまでも若々しく健康的に過ごすには
『腎』を健やかにすることがポイントということですね☆
〇漢方でみる冬の過ごし方
東洋医学の古典では
冬の3か月は『閉蔵』の季節とされています。
「蔵を閉じて内側に温存する」
といったイメージ。
春から育て、夏にパワーを沢山浴び、秋に収穫したものを冬に温存する。
動植物や作物だけでなく私達人間も同じで
水分(陰)やエネルギーを(陽)を発散、消費しすぎないことが自然の流れに添った冬の過ごし方です。
そしてこれが次の春からの1年の身体作りにも繋がります。
冬の過ごし方ポイント
①《早寝遅起き》
陰のパワーは夜、陽のパワーは昼に養われます。
消費よりも温存が大切な冬は
太陽に合わせ早く寝て遅く起きるのが理想的。
かといって現代人の私達は冬だから寝坊してもOKは難しいですよね。。。
そこで、他の季節よりも少し早く寝る事を意識してあげてください。
そして休みの日にはちょっと遅起きをしてみてくださいね(*^_^*)
➁《チャレンジしすぎない・頑張りすぎない》
身体だけでなく心の面でも冬は温存が大切。
沢山エネルギーを使いそうな新しいチャレンジや
やりたいことを沢山掛け持ちすることはできるだけ避けましょう。
内に込めて春からのチャレンジ!!として温めてあげるのがおすすめです。
また、冬の間は沢山汗をかく激しい運動よりも
散歩や緩めのヨガやストレッチ等
体をじんわり温める程度の運動がおすすめです。
〇冬の食養生
薬膳では『黒いもの』と『鹹味(塩辛い)』
は腎を養うとされています。
鹹味は私たちが連想するするしょっぱい味ではなく海産物やミネラルをイメージしてみてください。
確かに冬は美味しい海産物が沢山。。。(*ノωノ)
黒いもの
黒豆・黒糖・黒酢・黒ゴマ・レーズン・海藻・しいたけ・きくらげ・・・等
鹹味
牡蠣・あさり・いか・えび・醤油・味噌・海藻・・・等
一度に沢山ではなく
1日に1食、このうちのどれかを使った食事をしてみたり
何にもない時には黒ゴマや乾燥ワカメをプラスしてみたりと
冬の食養生をゆるく意識していただけたらと思います。
これから始まる冬
何か1つでも思い出していただけたら嬉しいです☆
ゆったり静かに温かく過ごしていきましょう✨
eatkampo Tsubasa